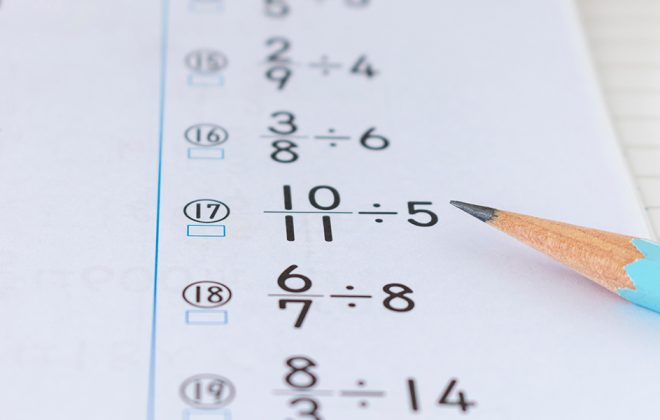「できないことをゼロに近づける」支援は、教育や発達支援の現場で長年、重視されてきました。 しかし今、その延長線に新たなアプローチとして注目を集めているのが「ニューロダイバーシティ(Neurodiversity)」です。
発達特性などの違いを「障がい」ではなく「個性」として捉え、強みとして社会の中で活かそうとするこの考え方は、教育現場や家庭にとどまらず、企業の人材戦略や社会のあり方そのものを変えつつあります。
本記事では、ニューロダイバーシティの基本的な考え方とその背景、企業・学校・家庭での実践例を紹介しながら、「ちがい」が力に変わる社会へのヒントを子どもの発達科学研究所 研究員の青山智士が紹介します。
一人の母親から始まった理念:ニューロダイバーシティとは
ニューロダイバーシティとは、脳や神経の機能的な違いを病気や障がいではなく「人間の自然な多様性」として尊重し、社会で積極的に活かそうとする考え方です。
自閉スペクトラム症(ASD)やADHDなどを不適応とみなすのではなく、「それぞれの個性」と捉えようというこの思想は、1990年代にオーストラリアの社会学者ジュディ・シンガー氏によって提唱されました。
彼女自身も発達に特性があり、また自閉症の娘を育てる母でもありました。従来、当事者たちが「できない人」として矯正や適応を求められてきた背景に対し、「ちがいを尊重し、共に生きる」社会を目指す運動としてこの概念は広まりました。
2000年代にはインターネット上で当事者同士の連帯が加速。2010年代以降は、IT企業を中心に、特性ある人材の能力に着目する動きが広がり、ニューロダイバーシティは社会変革のキーワードとなっていきます。
雇用コストではなく「才能への投資」として企業が注目
「一人ひとりが違う」前提から強みや特性を活かすニューロダイバーシティの考え方は今、企業の中でも急速に広がりを見せています。
きっかけとなったのは、ドイツのあるIT企業が自閉症のある人材をソフトウェアテスト業務に起用した結果、高度な集中力やパターン認識能力が極めて高い業績につながったという事例でした。
以降、企業において徐々に、発達特性は雇用リスクではなく、競争力の源泉=才能への投資と捉えられるようになりました。
また、発達障がいがある人の多くが無職、あるいは本来の能力を発揮できない職に就いているという現実もあります。ニューロダイバーシティは、埋もれていた人的資源を活かす鍵として、企業にとって戦略的な価値をも持っています。
日本でも、労働人口の減少や働き方改革を背景としニューロダイバーシティの概念は広がりはじめました。特に経済産業省が2019年頃から普及を推進し始め、同省主催の啓発セミナーでは参加企業の約9割が導入に意欲を示すなど、関心は高まり続けています。
このようにニューロダイバーシティは一時的なブームではなく、社会全体の変化を反映した概念といえます。
多様な人材登用に取り組む企業の実例
ニューロダイバーシティはすでに国内外の企業で採用・雇用プログラムとして導入されています。
- IT分野 マイクロソフト(Microsoft Corporation)、Google(Google LLC)、ヤフー(LINEヤフー株式会社)、デジタルハーツ(株式会社デジタルハーツホールディングス)など
- 金融分野 JPモルガン・チェース(JPMorgan Chase & Co.)、ゴールドマン・サックス(The Goldman Sachs Group, Inc.)など
- 製造分野 フォード・モーター(Ford Motor Company)、キャタピラー(Caterpillar Inc.)、P&G(The Procter & Gamble Company)など
これらの企業は、採用時には画一的な面接では見過ごされがちな才能を発掘できる手法を工夫し、業務においては多様な人材が活躍できる環境整備に力を入れています。こうした人材活用におけるニューロダイバーシティへの視点をご紹介します。
- イノベーションの源泉 特定の分野に集中力や分析力を発揮する人材は企業の生産性、品質、革新性を向上させ組織の新たな競争力になる
- 潜在的な人材層 例えばASD(自閉スペクトラム症)のある人の約8割が無職または能力以下の仕事に従事している調査があり、社会にまだ活かされていない才能が数多く眠っている
- 組織全体の活性化 ニューロダイバーシティを取り入れたチームでは、生産性、他の社員のエンゲージメント、チームの心理的安全性が向上するといった効果が報告されている
- 社会的な潮流 SDGsへの貢献はもとより支援対象だった人々が能力を発揮し納税者となることで、社会経済全体に大きなインパクトが期待される
併せて、国内の企業での活用事例をご紹介します。「ちがいが活きる」仕組みをつくる好例といえるでしょう。
サイボウズ株式会社では、在宅勤務や時差出勤など、社員が最も能力を発揮できる働き方を推奨しています。会議では口頭での議論が苦手でも、チャットでのテキストコミュニケーションが得意な社員が存分に能力を発揮できるような工夫がなされています。
また、LINEヤフー株式会社は障がいの有無で評価が変わることのない、公平な仕組みづくりを進めています。細かい点に気づく力や高い集中力を活かせるアプリの品質検証といった業務で、発達障がいのある社員が大きな戦力となっています。
教育・家庭で「ちがいを活かす」活用事例
教育や家庭でのニューロダイバーシティの活用は、個に応じた指導や合理的配慮などに当たる「その子に合った方法で学び、力を発揮できる」支援から始まります。
実践例としては、「特性」に合わせて学習手法を変えるのは有効です。漢字を覚えることが苦手な子はタブレットで絵や音と結びつけて記憶する、数字の概念をつかむことが得意でない子はブロックなどの具体物を使って視覚的に理解を促すなど、学習のつまずきの原因となっている特性に合わせ手法を変えていきます。
表現や評価の方法を画一的にしない工夫も大切です。実際の中学校の事例としては、書く、話す、描く・作るなど、子どもが得意な表現を選んで発表する取り組みなどが挙げられます。読み上げ機能や音声入力といったITツールの活用も選択肢を広げます。
こうした教育実践は、ライフスキルや将来のキャリア形成にも直結します。 子どもたちが「自分の集中しやすい環境」「理解しやすい方法」を知ることは、自己理解(メタ認知)を深める過程でもあります。自己理解に基づき成功体験を積み重ね、自信を育むことは、自分に合った働き方を選択し、社会で自立していくための重要な土台となります。
視点の転換が生みだす、社会を作る力
このようにニューロダイバーシティは、発達障がいを「欠点」ではなく「個性」と捉え、多様性を社会の力に変えていく考え方です。これは、障がいを個人の課題と捉える「医学モデル」から、社会全体のあり方を問う「社会モデル」へのシフトとも言えます。
今、企業も教育現場でも、この視点に立った制度づくり・環境整備が始まっています。一人ひとりが自分らしく働き、学び、生きていける社会は、誰にとっても生きやすい社会になるのではないでしょうか。
ニューロダイバーシティは、今後、こうした社会を作る力の原動力としてひとの「ちがい」を捉えるスタンダードになっていくことが期待されます。
執筆者:青山 智仁(あおやま ともひと)

- 公益社団法人 子どもの発達科学研究所 研究員
- 浜松医科大学 子どもの心の発達研究センター 特任研究員
- 公認心理士
- 袋井市子ども支援アドバイザー(静岡県)
- 所属学会:日本教育心理学会
参考文献
- Singer, J. (2016). NeuroDiversity: The Birth of an Idea.
- 経済産業省 (2023). 「イノベーション創出加速のための企業における「ニューロダイバーシティ」導入効果検証調査」
- 経済産業省 (2022). 「令和3年度産業経済研究委託費 イノベーション創出加速のためのデジタル分野における「ニューロダイバーシティ」の取組可能性に関する調査」.
- 野村総合研究所 (2021). 「デジタル社会における発達障害人材の更なる活躍機会とその経済的インパクト」
- Annabi, H., et al. (2019). “Autism @ Work Playbook”
- サイボウズ式.(2021)「大事にしたいものが自社ではなく社会なら、自然と「弱さ」に向き合っていきますよね──『マイノリティデザイン』澤田智洋」