子どもにスマホを見せておけば少し家事ができる、お気に入りの動画で機嫌が直った――。そんな子育て経験、ありませんか? 現代の育児においてスマホやタブレット、テレビは、ある意味“救世主”のような存在です。けれど、ふと「こんなに長時間見せていて大丈夫かな……」と心配になることもあるのではないでしょうか。
乳幼児の「スクリーンタイム」(テレビやスマホ、動画などの視聴時間)は子どもの発達にどんな影響を与えるのでしょうか。近年、科学的に調べた研究が増えてきました。
そこで今回は、子どもの発達科学研究所 主席研究員の和久田学が、注目すべき2本の論文から子育てに役立つ2つの視点をご紹介します。どちらも日本の研究チームによるもので、いずれも国際的に権威ある医学雑誌『JAMA Pediatrics』に掲載されたものです。
1歳のスクリーンタイムが、2歳・4歳の発達に影響
1歳児のスクリーンタイムが、発達に影響を及ぼすことを明らかにした研究があります。東北大学などの研究グループが行った「東北メディカル・メガバンク計画 三世代コホート調査」のデータを使った大規模研究です。(コホート研究とは、いわゆる追跡研究のこと)
7,097人の親子を対象に、1歳時点でのスクリーンタイムと、2歳・4歳時点での発達の関係を調べました。(※1)
その結果、スクリーンタイムが長いほど、コミュニケーションや問題解決の能力の遅れが生じるリスクが高まることが明らかになりました。
たとえば、1歳のときにスクリーンタイムが1日あたり「4時間以上」だった子どもは、「1時間未満」の子どもと比べて、2歳時点のコミュニケーション能力が遅れているリスクが4.78倍、4歳時点では2.68倍も高いことがわかっています。
また、問題解決能力についても、2歳で2.67倍、4歳で1.91倍という高いリスクが見られました。
逆に、身体を大きく使う粗大運動への影響は確認されませんでした。つまり、「言葉のやりとり」や「考えて工夫する力」など、人との関わりや思考に関わる発達が特に影響を受けやすいという結果になったのです。
この論文の結果は衝撃的です。ついつい頼りたくなるスマホや動画が、子どもの発達、それも言葉やコミュニケーション、思考に関わることに悪い影響を与えていることがわかったからです。
しかもその影響は、スマホや動画の内容に関係ありません。たとえ教育的に意味があるものだったとしても変わりないということになります。
おそらく幼い子どもにとっては、一方的に見たり聞いたりするだけのスマホや動画よりも、やりとりがあるリアルなコミュニケーション、豊かな感覚を伴った体験の方が重要だということでしょう。
一方で、「そんなことを言われても困る」という意見もあるのではないでしょうか。
大人だってスマホや動画を楽しんでいます。それどころか、子育ての状況として頼らざるを得ないときだって多々あるはずです。育児に便利なアプリも増えています。
少しは時間を減らすことはできても、ゼロにすることは難しいです。今や、スマホや動画のない生活は成立しないと言っていいほどなのですから。
「外遊び」が影響を和らげてくれる
では乳幼児期のスマホ育児は絶対にダメなのでしょうか。もう1つご紹介したい研究結果があります。
それは「外遊びをすればスクリーンタイムの影響が和らぐ」というものです。
「浜松母と子の出生コホート研究(HBC Study)」では、885人の子どもを対象に、2歳時点のスクリーンタイム(テレビ、スマホ、動画等)が4歳時点の発達にどう関係しているのか、さらに「外遊び」がその関係を弱める可能性があるかを調べました(※2)。
その結果、2歳でスクリーンタイムが1時間以上だった子どもは、4歳でコミュニケーションや日常生活のスキルがやや低下する傾向が見られました。
しかし、ここからがこの研究の大切なところなのです。
同じようにスクリーンを1時間以上見ていても、「2〜4歳の間に週6日以上、外で遊んでいた」子どもたちは、日常生活スキルの低下が明らかに“緩和”されていました。
つまり、「たくさん動画を見せてしまったからもう手遅れかも……」とは言い切れません。外での遊びが、その影響を和らげてくれる。そんな希望のある結果です。
一方で、外遊びをしていても、スクリーンタイムがコミュニケーションスキルに与える負の影響は緩和できませんでした。こうした負の側面も同時に理解しておく必要があります。
スクリーンと上手に付き合うために
これらの研究は「スクリーンは絶対にダメ!」ということを言っているわけではありません。
大切なのは使い方です。日々の生活の中で、次のようなことを意識してみませんか。
- 「なんとなくつけっぱなし」になっていないかな?
- 「親子で一緒に」楽しめているかな?
- 「知育的なコンテンツ」を選んでいるかな?
- 「外遊びの時間」はきちんと確保できているかな?
WHO(世界保健機関)も、2歳未満の子どもには原則としてスクリーン視聴を推奨しておらず、2歳以上でも「1日1時間以内」が目安とされています。
特に長時間にならないようにすることが大切です。また、外遊びに限らず、どれだけスクリーン以外の遊びをし、スクリーンから離れた時間をどう過ごすのか。こうしたことがさらに重要になってきます。
何より大切なのは、スクリーンの代わりに「実際の体験」をすること。
外での遊び、友だちとの関わり、自然とのふれあい――これらはすべて、子どもの発達にとってとても豊かな栄養です。これらはこれまでも経験的に「当たり前」だとされてきたことではあるのですが、それに科学的な裏付けが得られたということが重要です。
科学は「不安」を和らげる道しるべに
今回ご紹介した2つの研究は、どちらも非常に信頼性の高いデータに基づいたものです。
そして、どちらの研究にも共通して言えるのは――
スクリーンタイムは長すぎると発達に影響があることは明らかです。でも、外遊びなど他の活動、体験を豊かにすること次第で、その影響は変えられるのだ、という親として希望を持てるメッセージです。
子どもが泣き止まず、ついスマホを手渡してしまった日。家事と育児の両立で精一杯だった日。
そんな日があってもいいのです。
大切なのは、今日から、少しずつ工夫してみること。そして、外でのびのびと遊ばせてあげること。科学は、親を責めるためにあるのではなく、より良い選択を応援する「道しるべ」なのです。
執筆:和久田 学(わくた まなぶ)
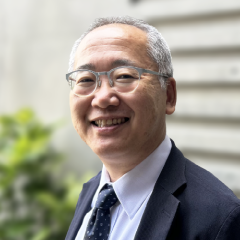
- 公益社団法人子どもの発達科学研究所 所長・主席研究員
- 大阪大学大学院 大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学 連合小児発達学研究科 招聘教員
- 博士(小児発達学)
- 専門は発達心理学、教育学
- 所属学会:特殊教育学会、LD学会、自閉症スペクトラム学会、子どもいじめ防止学会
参考文献
※1 Takahashi I, Obara T, Ishikuro M, et al. (2023). Screen Time at Age 1 Year and Communication and Problem-Solving Developmental Delay at 2 and 4 Years. JAMA Pediatr. doi:10.1001/jamapediatrics.2023.3057
※2 Sugiyama M, Tsuchiya KJ, Okubo Y, et al. (2023). Outdoor Play as a Mitigating Factor in the Association Between Screen Time for Young Children and Neurodevelopmental Outcomes. JAMA Pediatr, 177(3), 303–310. doi:10.1001/jamapediatrics.2022.5356









