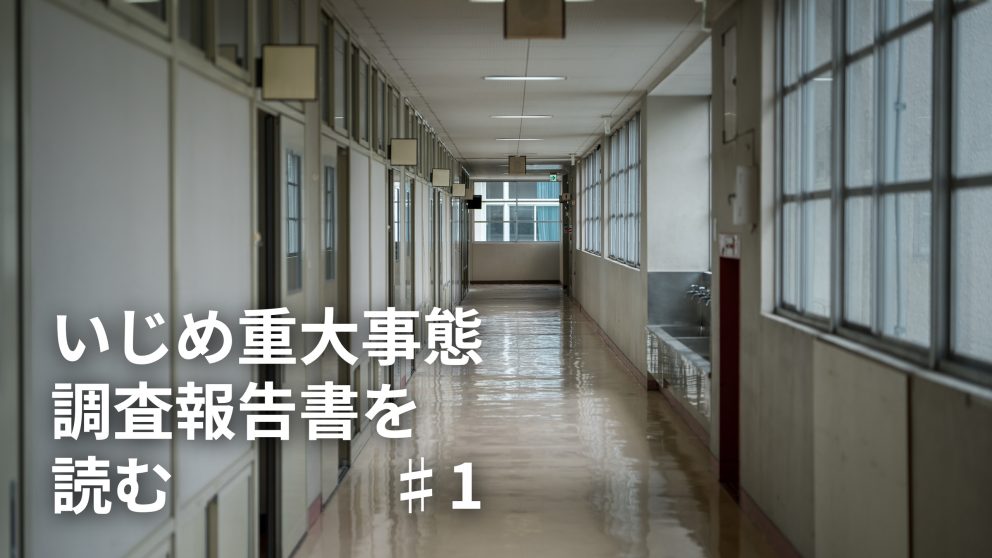学校生活には、授業や行事などさまざまな活動があります。ボールを投げる、字を書く、ハサミを使うといった多様な動作が含まれますが、そうした動きをうまく行えない子どももいます。その理由の一つとして考えられるのが、「発達性協調運動症(DCD: Developmental Coordination Disorder)」です。
まだ日本では認知度が高くないDCDの特徴や周囲の大人が取るべき接し方について、子どもの発達科学研究所 副主任研究員の津久井伸明が解説します。
目に見えにくい「不器用さ」が学校生活に与える影響
「どうしてこの子はこんなに手際が悪いのだろう」「何度教えても上達しないのはなぜ?」。そんなふうに感じたことのある教師や保護者も少なくないでしょう。
小学校の教室では、日々さまざまな活動が行われています。ノートを取る、跳び箱を跳ぶ、給食を配る、図工の作品をつくる。こうした「当たり前」のような動作が、実はとても苦手な子どもたちがいます。
背景には、発達性協調運動症(以下、DCD)やその傾向が関係している場合があります。DCDは、知的な遅れがないにもかかわらず、動作のぎこちなさや不器用さによって、日常生活や学習活動に支障が出る神経発達症のひとつです。
海外では教育・医療の現場で広く知られ、学校での合理的配慮や専門的支援が進んでいますが、日本ではまだ認知度が高くないため、本人の努力不足や家庭環境の問題と誤解されてしまうことも少なくありません。
しかし、実際には脳と身体の協調に関わる神経的な偏りによって生じることが、明らかになっています(※1)。
本稿では、小学生の発達段階や心理・社会的な背景をふまえ、「学校生活における不器用さ」について、具体的な行動例、望ましくない対応、そして科学的根拠に基づく支援のあり方について考えていきます。
不器用な子どもが学校でしてしまいがちな行動の具体例
DCDやその傾向のある子どもたちは、次のような行動で困難さを示すことが多いです。
- 体育の縄跳びや跳び箱がうまくできず、すぐに諦めてしまう
- 図工で線に沿って切るのが難しく、作品が思い通りに仕上がらない
- 給食の配膳中に食べ物をこぼしてしまう
- 板書のスピードについていけず、ノートの字が乱れている
- ランドセルの金具に給食袋や体操着袋をうまく付けられない
- 体操着袋の紐や靴紐を結ぶのが難しい
- 忘れ物が多く、提出物の管理が苦手である
こうした行動は、一見すると「やる気がない」「だらしない」「注意が足りない」と見なされがちです。しかし、実際には本人なりに精一杯努力していることが多く、その努力が報われないことへのフラストレーションが自己否定感につながりやすいのです。
とくに中学年以降は、友人と自分を比較する場面が増え、「どうして自分だけできないのか」と悩む気持ちが強まっていきます(※2)。
大人がやってしまいがちな望ましくない対応
子どもの不器用さに対して、大人がとる対応の中には、本人の気持ちや背景に配慮していないものもあります。
保護者による対応の例:
- 「もっと丁寧にやりなさい」と繰り返し叱る
- 「お兄ちゃんはできたのに」など、きょうだいと比較してしまう
- 失敗を避けるために、先回りして代わりにやってしまう
教員による対応の例:
- 図工や体育で、本人に相談や配慮なく、機械的に本人だけ別メニューにしてしまう
- ノートの取り方を繰り返し注意するが、改善方法は示さない
- 「やればできるはず」と努力だけを強調する
このような対応は、本人の「できない」という気持ちに対する焦りや不安をさらに強めかねません。とくに「他の子はできているのに」という比較や、本人の性格の問題と受け止められるような言い方は、自己肯定感の低下につながります(※3)。
科学的根拠に基づく望ましい対応
ではどのような対応が望ましいのでしょうか。ここでは、科学的根拠に基づいた4つのポイントを紹介します。
1.具体的な支援と環境調整
DCDのある子どもは、「やりたいけれどうまくできない」という気持ちと行動の両面で困難を抱えています。
こうした特徴を踏まえ、動作や学習における工程を分解し、視覚的に提示する工夫や、道具の選び方を調整する配慮が効果的であるとされています(※4など)。
以下に、好ましいと考えられる対応を挙げます。
- 書字には、ガイドライン付きのノートやタブレット入力を併用する
- ハサミは滑り止め付きのものを使用し、図工では作業工程を視覚化する
- 体育では、跳び箱を分解して段階的に練習したり、動きを写真で示したりする
- ロッカーや持ち物管理にチェックリストや色分け表示を使う
- 課題の提示方法を口頭+視覚(例:ホワイトボード・イラスト)で併用する
これらは「特別扱い」ではありません。DCDという明示はありませんが、文部科学省(※5)や内閣府(※6)が例示する合理的配慮に基づいた正当な教育的支援です。
2.成功体験を積ませる
不器用さのある子どもにとって、「できた!」という実感を積み重ねることは、学習意欲と自己効力感を育てるうえで非常に重要です。小さな成功に注目し、段階的な目標設定で肯定的なフィードバックを行うことが有効だと報告されています(※7、※8)。
次のような工夫が有効です。
- 体育や図工では、完成度より「工夫や挑戦」に注目する
- 「前よりうまくできたね」と本人の中での成長に焦点を当ててフィードバックする
- 実際にできたときには大きく共感する声かけをする
- 得意な部分を「役割分担」し、集団の中で役目を果たせる経験を保証する
3.「不器用さ」の意味を子どもと共有する
子どもが自分の不器用さや困難を理解し、向き合う方法を一緒に考えていく。このような関わり方は「自己理解支援」と呼ばれ、近年注目されているアプローチのひとつです。
子ども自身が、自分の得意・不得意や困難の意味を理解することで、安心感と主体性を得やすくするのが目的です(※9)。
「あなたの脳からの情報が体に届くまで少し時間がかかる」といった説明が、自尊感情を支えます。
また、「どんな工夫があるとやりやすい? 」と一緒に考えることは、自己調整力の育成にもつながるのです。
4.クラスメイトへの理解づくり
DCDのある子どもは、周りの視線を気にして活動に参加しにくくなることがあります。そのため、クラス全体で多様性を尊重する空気づくりが重要です。
教師による短い説明や日常的な声かけを通じて、「みんなちがって、みんないい」という雰囲気を育てましょう。
クラスメイトの理解が深まることで、DCDの子どもが積極的に活動に参加できるようになるというケースが、複数の研究で示されています(※10)。
子どもが「自分らしく学べる」場づくりを
不器用さの背景には、持って生まれた脳機能の多様性があります。発達性協調運動症(DCD)やその傾向を持つ子どもたちは、「努力してもうまくいかない」つらさのなかで、日々学校生活を送っています。
だからこそ、私たち大人がその特性を理解し、「どうすればこの子が力を発揮できるか」を考え続けることが大切です。
子どもたちが「このままの自分でも大丈夫」「できることを増やしていける」と思えるような環境づくりを、家庭や学校が一体となって支えていきましょう。
執筆者:津久井 伸明(つくい のぶあき)

- 公益社団法人 子どもの発達科学研究所 副主任研究員
- 浜松医科大学 子どものこころの発達研究センター 特任研究員
- 修士(教育学)
- 博士(小児発達学)
- 公認心理師、臨床発達心理士、特別支援教育士SV
- 特別支援教育士資格認定協会 養成委員会委員
- 所属学会:教育心理学会、LD学会、DCD学会、児童青年精神医学会、脳科学会
参考資料
※1 Brady, D., & Leonard, H. (2020). Developmental Coordination Disorder. In The Oxford Handbook of Developmental Cognitive Neuroscience.
※2 Lapan, C., & Boseovski, J. J. (2017). When peer performance matters: Effects of expertise and traits on children’s self-evaluations after social comparison. Child Development, 88(6), 1860–1872. https://doi.org/10.1111/cdev.12941
※3 Dweck, C. S. (2006). Mindset: The new psychology of success. Random House.
※4 Iwamoto, K., Pines, K., Lochala, C., Long, D., Hess, P., & Sargent, B. (2025). Systematic review to inform the Developmental Coordination Disorder clinical practice guideline update: Physical therapy intervention. Pediatric Physical Therapy. Advance online publication. https://doi.org/10.1097/PEP.0000000000001177
※5 文部科学省. 別紙 2 「合理的配慮」の例. 中央教育審議会特別支援教育部会答申資料. https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1297377.htm (2025年8月20日閲覧)
※6 内閣府. 合理的配慮サーチ:教育分野の事例集. https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/index_kyouiku.html (2025年8月20日閲覧)
※7 Caçola, P., Romero, M., Ibana, M., & Chuang, T.-W. (2020). Impact of a summer camp for children with DCD: Self-perception, motor skills, and social participation. Human Movement Science, 72, 102669.
※8 Missiuna, C., Gaines, R., & McLean, J. (2017). Promoting participation of children with DCD: A model of intervention planning. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics, 37(1), 1–15.
※9 Kirby, A., Edwards, L., & Sugden, D. (2019). Emerging support needs of children with developmental coordination disorder. British Journal of Special Education, 46(1), 5–23.
※10 Kirby, A., Wilmut, K., & Missiuna, C. (2022). A global review of interventions for children with DCD. Child: Care, Health and Development, 48(2), 163–178.