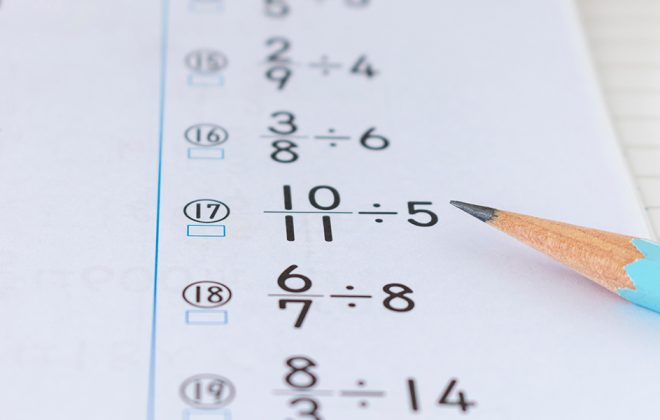すべての企業および国・地方公共団体における障がい者の法定雇用率が段階的に引き上げられていく中、「合理的配慮」は雇用者、被雇用者、双方にとって幸福な雇用関係構築のカギと言えるかもしれません。
しかし、「合理的配慮」を語るとき、避けては通れないのが「どこまでが合理的配慮なのか」という議論。
明確な線引きが難しいこの課題をどう考えていけばよいのか。1つの指針を示してくれるのが、書籍『合理的配慮 ー対話を開く,対話が拓く』(川島聡 他、有斐閣)です。
本書について、子どもの発達科学研究所 主任研究員の大須賀優子が紹介します。
合理的配慮とは何だろう?
2016年4月、「障害者差別解消法」「障害者雇用促進法」の一部改正が施行されたことに伴い、わが国の法制度の中にそれまで存在しなかった「合理的配慮」という概念が導入されました。
これを機に、学校や行政機関などの公的機関においては、障がい児者へ合理的配慮の提供が義務付けられ、事業主は障がい者雇用に際し合理的配慮の提供を求められるようになっていきます。
更に8年後の2024年には「障害者差別解消法」が改正され、この合理的配慮の提供義務は、民間事業者にも広げられました。
さて、この10年近くの間に、果たして、この言葉は社会に十分馴染み、私たちは「合理的配慮」を正しく理解し、しかるべき場面で適切に提供することができるようになったのでしょうか。
残念ながら、その答えは「NO」であるように思われます。
もちろん以前に比べれば、状況は改善しています。しかし、そもそも、それまでの私たちの社会になかった新しい概念を社会全体に広く馴染ませるということは、なかなかに手間がかかるものです。
さらに、合理的配慮を理解するには、その前提として、「差別とは何か」「社会的障壁とは」「なぜ合理的配慮の提供が求められるのか」といったことも理解する必要があり、簡単ではありません。
今回、この『合理的配慮 −対話を開く,対話が拓く』の紹介をするのは、ひとえに、「合理的配慮」を正しく理解し、この概念で提示された社会を真に実現していくために、ここに書かれていることが非常に役立つはずであると考えるからです。
この本において合理的配慮とは、「基本的に,(1)個々の場面における障害者個人のニーズに応じて,(2)過重負担を伴わない範囲で,(3)社会的障壁を除去すること,という内容を持つ措置」であると説明しています。
そして、ここで繰り返し語られるのは、合理的配慮の提供には「対話」を欠かすことはできないということです。
2つの「差別」のかたち
合理的配慮の提供は、障がい者への差別を解消するための措置です。そこで、障がい者に対する差別とは何か、あらためて整理する必要があります。
この本は、歴史的な経過をたどり、差別には2種類あることを教えてくれています。「等しい者を異なって扱う型の差別」と「異なる者を異なって扱わない型の差別」です。
通常、「差別とはどのような行為か」と問われた際、私たちの頭にまず浮かぶのは、「不当に権利をはく奪する行為」ではないでしょうか。同じ人間なのに、同じ権利を有しているのに、同じように扱われないことが差別である、という考えです。
たとえば、聴覚障がいがある人が医療機関にかかろうとして断られる、といったケースが、これに該当します。あるいは女子学生が大学入試で、女子であることを理由に不合格になる、といったことです。
誰しも、同じように医療を受ける権利、平等に扱われる権利を持つはずであり、その権利(機会)を何らかの理由で奪われていることが差別である。つまり「等しいものを異なって扱う型の差別」がこの例に当たります。
一方、こちらの例はどうでしょうか。
読み書き障がいのある人が、就業中に必要なマニュアルの提供方法として、通常の紙のマニュアルではなく、音声変換が可能なデジタル形式を希望した。しかし、上司から「時間をかけて読めばわかるでしょう」、「そんなコストはかけられない」と言われてしまった。
あるいは、本書の中でこんな実例も紹介されています。
ある男性が宗教的信念に基づき軍服を着ることを拒否したため有罪判決を受け、この犯罪歴を理由に公認会計士職に就くことができなかった、という実例です。
これは、実際に2000年にギリシャで起こった事件であり、後に欧州人権裁判所が、「他の重大な犯罪者と男性を異なって扱うべきであり、例外を設けなかったことは違法である」という判断を下しています。
さて、読み書き障がいの例で示されたのは、ギリシャの実例と同様、「異なる者を異なって扱わない型の差別」になります。
読み書きが困難であるという異なった状況にある人に対して、紙マニュアルをデータ形式で提供するというように、例外として扱わなかったからです。現在であれば、これは「合理的配慮不提供」として、障害者差別法違反に問われる問題になります。
この「異なる者を異なって扱わないことは差別である」という考え方は、2000年頃に急速に世界中に広まりました。
本書では、その背景に合理的配慮の概念を初めて世に知らしめた「障害をもつアメリカ人法(ADA)」(合衆国法典、1990年制定)の成立があり、そしてこの新しい考え方は、2006年、ついに「障害者権利条約」という形で結実した、としています。
すなわち、この条約の批准国である日本においても、冒頭に挙げた「障害者差別解消法」「障害者雇用促進法」等の法整備を行い、この「障害者権利条約」に掲げられた理念を、実際の暮らしの中で、実現していくことが求められているといえるでしょう。
「等しい者を異なって扱う型の差別」と「異なる者を異なって扱わない型の差別」を取り除くために、合理的配慮として、必要な変更や調整を提供していくことが必要とされているのです。
人々が新しい考え方に対して不安を感じ拒否しようとするのは、往々にしてよくあることです。しかし、このように、世界的な約束事として定められ、国内法でも明確に規定されている以上、合理的配慮の提供について、私たちはどのような事業を行う上でも、等しく義務を負っていることを忘れてはならないと思います。
「社会的障壁」を取り除くのは社会の側の義務
強く心を惹(ひ)かれる箇所として、本書における以下の指摘があります。
この社会は、多数派(非障がい者)向けの社会環境になっていて、多数派(非障がい者)と少数派(障がい者)の間で、享受できる利益に大きな落差があるとする指摘です。
熊谷晋一郎氏の言葉を借りれば、「障害とは、少数派の身体的特徴をもつ人々と、多数派向けの社会環境との『間』に宿るもの」であり、多数派向けの社会環境の中で、少数派の身体を持つ人々が経験する困難こそが障がいであるともいえます。
これらの視点から見ると、この不均衡な社会構造をこのままにしておくわけにはいきません。
そして、こうした社会構造を変えていくために提供されるべきは、合理的配慮であるといえます。(実は、もう1つポジティブアクションという大事な概念もありますが、その内容や合理的配慮との違いについて、本書に詳しく記載されていますので、是非そちらでご確認ください)
先ほどの例で、読み障がいの人に対して、みんなと同じように紙のマニュアルを使ってくださいと言った上司には、「障がいは本人の中にある、その障がいを乗り越えるべきは本人」という意識があるのかもしれません。
しかし、障害者権利条約で謳(うた)われているように、障がいは環境による障壁(物理的環境や社会環境、人の態度など)と本人の心身の機能障がいとの間の相互作用、いわゆる「障がいの社会モデル」であり、その障壁を取り除く責任は社会の側にあるのです。
読み書きに困難がある人が通常の紙のマニュアルに困難を感じているとき、それを「本人の努力不足」と見るか、それとも「異なる状況の者へ、その違いに合わせた労働環境が提供できていない」と見るかで、対応は大きく異なります。
本書は、後者の視点に立ち、「障がい者の社会的障壁を個人の問題にせず、社会の側が環境や制度を変えていくことこそが合理的配慮の本質」であると明快に示してくれます。
合理的配慮に欠かすことができない「対話」
さて、最後に「対話」についても、少しだけ触れておきます。合理的配慮の提供には「対話」が欠かせない、と本書では繰り返し語られています。
個性に応じた合理的配慮を行うためには、どうしても、相手の声に耳を傾け、その一方で自分は何ができるのかを伝え、両者が納得して折り合う地点を見出さなければならないからです。
少数派の人に多数派の人々が、この不均衡な社会を強いている。この事実に目を向け、互いに相手を尊重するという基本的な態度を持ちつつ、こうした対話による営みを続けていくことで、この社会の不均衡は少しずつ解消されていくのではないでしょうか。
また、さらに忘れてはならないのは、誰しも合理的配慮を求められる立場になることもあれば、求める立場になることもある、ということです。
対話なくして合理的配慮無し。この意味を深く理解し、自分事として対峙するためにも、是非とも本書を手に取っていただきたいと思います。
執筆者:大須賀 優子(おおすか ゆうこ)

- 公益社団法人 子どもの発達科学研究所 副所長・主任研究員
- 博士(小児発達学)
- 所属学会:日本児童青年精神医学会、日本教育心理学会
参考文献
- 川島聡 , 飯野由里子, 西倉実季 , 星加良司(2016)『合理的配慮 ー対話を開く,対話が拓く』有斐閣
- 熊谷晋一郎(2022)「当事者研究から学ぶこと」『小児内科 54巻7号』pp.1102-1106 東京大学先端科学技術研究センター