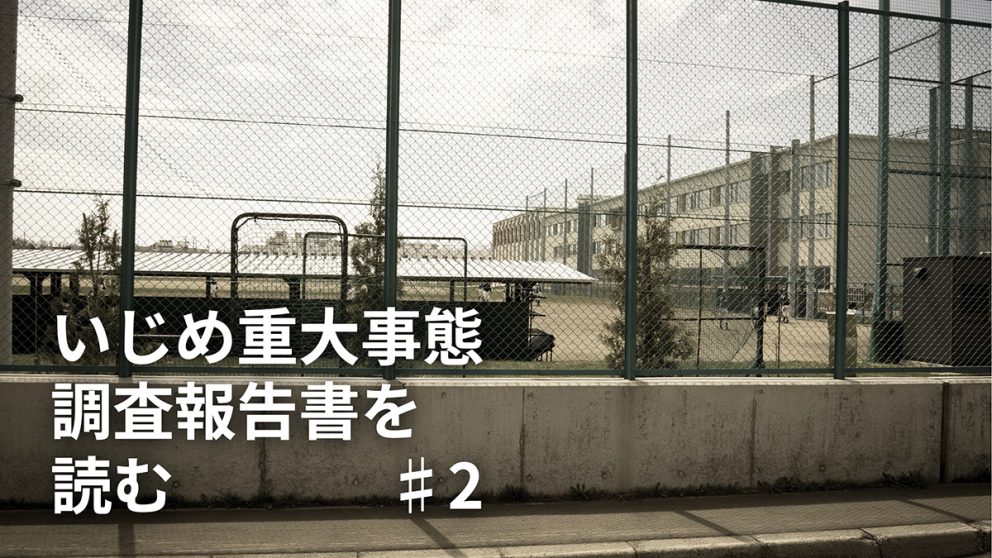長い夏休みが終わり、新学期を迎えると、子どもが「学校に行きたくない」と訴えることがあります。不登校と聞くと思春期以降の子に多い印象がありますが、近年は小学1年生を含め低学年に増えているという調査結果も出ています。低学年の子どもは、まだ自分の気持ちをうまく言葉にできないことが多いため、親はどう受け止めればよいのか不安になりがちです。そんなとき、どう対応すればいいのかについて、子どもの発達科学研究所 所長で主席研究員の和久田学氏に伺いました。
(取材・執筆:コハツWEB取材班)
低学年の不登校が増加 背景には「発達の変化」
ーー文部科学省の調査によると、2021年度〜2023年度の3年間で、小学1年生の不登校児童数が2.02倍に増加しています。高学年と比べて低学年の増加率が大きくなっていますが、低学年の不登校が増えている背景について教えてください。
以前から「低学年の子が落ち着かない」「母子分離ができない」という問題はありました。入学したばかりの1年生が学校生活にうまく適応できない「小1プロブレム」という言葉も20年以上前からあります。そういう子どもたちが不登校という選択ができるようになってきた、と理解するといいと思います。
なぜ今低学年で不登校が増えているのか。背景には子どもの発達の変化があると考えられます。
子どもの発達は環境に大きく影響されます。私が子どもの頃は、近所の子どもが集まって群れて遊んでいました。でも今はどうでしょうか。遊びは集団から1対1やバーチャルな世界、デジタルコンテンツを通じた関わりへと変わりました。
子どもはコミュニケーションのやり方を身近な大人である親から学びます。しかし、大人同士のコミュニケーションの中心は、対面からSNS上へと移りました。 その結果、子どもが大人のやり取りを直接見聞きする機会は少なくなっています。
たとえば、励まし合う姿や問題を解決する過程、愚痴を言い合う様子などに触れることが減り、子どもは大人を手本にしてコミュニケーションの方法を学びにくくなっているのです。こうした子どもの遊びや経験、環境の変化が、子どもの社会性の発達やコミュニケーションスキルに影響を与えていると考えられます。
変わらぬ学校環境が生活とミスマッチ
ーー生活環境は親世代と比べて大きく変わりましたが、学校では大人数が一斉に授業を受けるスタイルのままです。こうしたギャップが何か影響しているのでしょうか。
その通りで、学校では時代に合わせた変化が見られる一方で、昔ながらのスタイルも多く残っているケースがあります。たとえば、小学校低学年であっても「自分の席に座る」ことが集団生活のルールとされ、それを前提に学校生活が組み立てられています。決まりごとのある学校生活と、家庭での自由な生活との間に乖離があり、ミスマッチが起こるわけです。今の学校の居心地が、今の子どもたちの発達段階に合っていない可能性があります。
こうした、学校と家庭のミスマッチに加えて、社会環境の変化も不登校を後押ししています。不登校に対する親の理解が軟化してきた、というのも不登校が増えた一つの理由でしょう。「行きたくないなら行かなくてもいいんじゃない?」と考える人が増え、ハードルが下がってきたのです。
さらに、コロナ禍も影響しています。コロナ禍では家で過ごすことが当たり前になり、両親も家で仕事ができる環境になりました。家にはYouTubeやゲームなどもある。「学校より家の方が楽しい」という環境が整ったわけです。
こうしたさまざまな背景から、低学年から不登校を選択する子どもが増えたと考えられます。
「学校に行きたくない」と言われたら SOSを受け止めて
ーー2学期が始まって早々、低学年のわが子から「学校に行きたくない」と言われたら、親はどう対応すればよいですか。年齢が低いと自分の気持ちをうまく言語化できないこともあります。すぐに子どもの要求を受け入れてよいものでしょうか。
親の対応については「こうすればいい」という方程式は存在しません。親から「行ってこい」と送り出され、「行ってみたら案外楽しかった」という子もいます。でも、全ての子どもにそのやり方が合うとは限りません。
最終的には親がわが子の発達やレジリエンス(逆境から立ち直る力)に合わせて、調整する必要があります。
弊所(子どもの発達科学研究所)の基本的な考え方では、「学校へ行きたくない」という言動は援助要請であり、子どもからのSOSと捉えるべきだとしています。
「そうなんだ」「行きたくないんだ」と受け止め、丁寧に状況を把握して対応することが原則です。
小さい子は不安な気持ちを言葉にできないことが多いです。理由がはっきりわからなくても、まずは子どもの気持ちを尊重し、安心できるよう寄り添ってあげましょう。そのうえで、「どうして不安を感じるのかな」といった声かけをして、子どもの気持ちを丁寧にくみ取っていくことが大切です。
「あなたが弱いからでしょ」などと言ってしまうと、子どもは「親にはSOSが出せない」と学んでしまいます。
昔であれば、お父さんお母さんがダメならおばあちゃん、近所のおじさんといろいろな選択肢がありましたが、今は子どもや家庭が孤立しているケースが少なくありません。そうした状況で保護者が子どものSOSを受け止められないと、周りに助けを求めること自体をしなくなる可能性があります。
あるいは、ネットで相談するようになるかもしれません。ネットでは、悪意のある大人とつながる危険性もありますし、メンタルヘルスのさらなる悪化やリストカットなど深刻な行動につながるリスクも高まります。
子どもがSOSを出したとき、きちんと受け止めてくれる大人が身近にいることが、安心感や愛着につながります。そういう親子関係を日頃から築いてほしいというのが、私からのメッセージです。
SOSサインは体調・生活・行動に表れる
ーー親は子どものどのような言動を「SOSサイン」として受け止めればよいでしょうか。
SOSは体調不良や生活リズムの乱れ、行動の変化に表れます。
体調不良は「気分が悪い」「元気が出ない」「お腹や頭が痛い」「だるい」「熱っぽい」などで、生活リズムの乱れは「朝起きられない」「夜眠れない」「お腹が減らない」「便秘になる」などです。
食事や着替えなど、できていたことが急にできなくなる行動の変化もSOSだと思ってください。
今まで1人でごはんを食べていたのに、急に「あーんして」と言うことも。トイレの補助を求める、なかなかごはんが終わらないといった場合も気にかけてあげてください。変化に親が敏感であることが大事です。
本音を引き出すコツは接触と安心感
ーー子どもから明らかなSOSサインが出ているのに「なんでもない」と言われたら、どう対応すべきでしょうか。
子どもの本音を引き出すコツがあります。たとえば「接触」です。まだ低学年であれば、抱っこしながら話を聞いてみると、本音を引き出せることがあります。接触は「あなたを守っているよ」というメッセージになるからです。
もう1つのコツは、時には冗談を言って、にっこりとさせること。緊張すると本音は言えません。笑って心がほぐれると言葉もほぐれます。
また、「本音を言っても絶対に傷つけたり責めたりはしない」という安心が前提でないと本音は言えません。本音を言ってくれたら、まずは全肯定してあげてください。子どもの言葉を事実として受け止める存在が親であってほしい。
たとえ嘘だと分かっていても、否定をせず、あえて振り回されることも必要です。たとえば、明らかに元気そうなのに「お腹が痛いから学校に行けない」と訴えてきた場合、「そうか、痛いんだね。つらいね」と一度受け止めてあげてください。そうすると、子どもは「自分の思いを受け止めてもらえた」と安心し、やがて本音を話せるようになります。このように、低学年のうちから子どもと親の信頼関係を築いておくと、成長して心が揺れやすい思春期を迎えても本音を伝え合える親子関係を保ちやすいです。
不登校でなくてもそうですが、「親は子どもの味方である」ということを、行動でも言葉でも示し続けるべきです。「あなたは一生懸命やってるよ」と言ってあげてほしいですね。
低学年の付き添い登校は「気が済むまで」
ーー「ママ(パパ)とだったら行ける」と、付き添い登校を望む子どももいます。いつまで続くのか親は心配になってしまいますが、気の済むまで寄り添ってあげるべきでしょうか。
子どもが要求しているなら、要求通りにしてあげるといいと思います。付き添って気が済むなら付き添ってあげればいい。
永遠に親に付き添ってもらう子どもはいません。中学生にもなると、自分で不登校を選択できるようになるからです。発達段階が進むにつれて、子ども自身が自分なりの結論を見い出せるようになっていきます。 ただし、中には深刻なケースも存在するため、スクールカウンセラーのような、発達の専門家の意見を取り入れて対応することも重要です。
付き添いが難しい場合は、子どもと話し合ってみてください。 子どもは「自分のことをすごく考えてくれている」という前提があれば、案外交渉に応じるものです。子どもだってママパパのことが大好きですからね。
監修:和久田 学(わくた まなぶ)
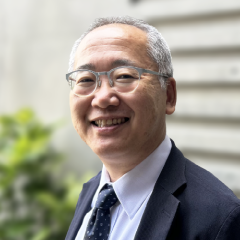
- 公益社団法人 子どもの発達科学研究所 所長・主席研究員
- 大阪大学大学院 大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学 連合小児発達学研究科 招聘教員
- 博士(小児発達学)
- 専門は発達心理学、教育学
- 所属学会:特殊教育学会、LD学会、自閉症スペクトラム学会、子どもいじめ防止学会
参考資料
文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」