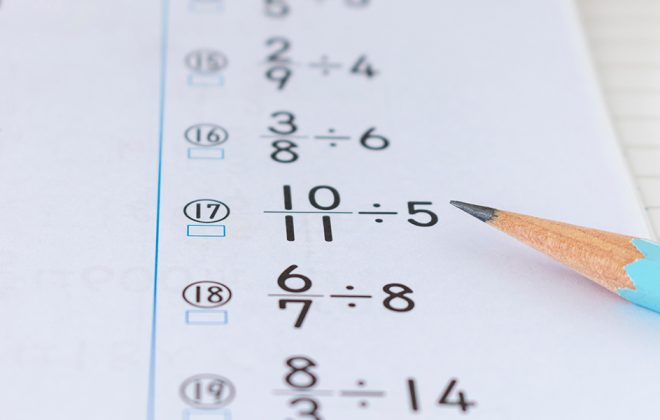人と話すのが好き、将来はサービス業で働きたい――。そんな希望を持っていたある青年が、今は静かな作業場で自動車部品の仕分け作業に黙々と取り組んでいます。
これまで接客業を目指してきましたが、失敗の連続。「集中する作業の方が向いている」という青年の特性に家族が気づくまで、約20年の歳月を費やしました。
障がいのある人の就労に対し、家族はどのように向き合い、サポートすればよいのでしょうか。仕事選びに必要な視点を巡る、リアルな声を取材しました。
2025年10月には障害福祉サービス「就労選択支援」が始まるなど、その人らしく働くことへの注目が高まる昨今。今後の働き方を考えるヒントにつながる家族の事例として紹介します。
取材・執筆:コハツweb取材班
特性に合う仕事にたどり着く難しさ…希望とのギャップも
軽度知的障がいと発達障がいが併存するアキラさん(40・仮名)。紆余曲折の末、3年前に自分に合う職に出会うことができました。
アキラさんは、子どもの頃から目立ちたがり屋で明るく、人と関わることが大好きでした。本人が希望したのは、制服を着てレジに立ち、顧客とやりとりをするサービス業。家族もその希望を応援しました。
特別支援学校高等部を卒業後、全寮制の県立職業訓練校へ。その後、地域障害者職業センターのジョブコーチ(職場適応援助者)の支援を受け、念願の大手飲食チェーン店に就職しました。
ところが、現実は甘くありませんでした。職場では臨機応変な対応や、複数業務を同時にこなす力、同僚との連携など、多くのスキルが求められます。アキラさんにとっては混乱の連続の日々でした。バックヤード業務に配置換えになったものの、「やりたいことではない」とモチベーションが保てず離職。こうして農家や家具店など、2年間で6回もの転職を繰り返したのです。
得意と好きはちがう 信頼するジョブコーチの勧めで知った適職
転職を繰り返すアキラさんは「自分には何ができるのか」と徐々に自信を失うように。そんなときに出合ったのが、収入は少ないけれど、よりマイペースに働ける就労継続支援B型の事業所でした。信頼するジョブコーチに勧められて始めたのは、自動車部品の仕分けという単純作業です。これまでになかった選択でしたが、静かな作業場で自分のペースでできる仕事が、アキラさんの特性に合っていることが判明したのです。
弟のショウタさん(仮名)は約20年間、母と共にそんな兄の苦悩を見守ってきました。
「安定した就労に向けて最もハードルが高かったのは、本人に合った働き方を探すことでした。兄は人と話すのが得意だから接客が向いていると、本人も家族も信じて疑いませんでした。でも実際は得意と好きがちがっていた。家族としては、こうした出会いにつながった担当者との相性は大変重要だったと感じています」(ショウタさん)
仕事内容に加え、現在の職場である事業所はアットホームな雰囲気で、アキラさんの思いにもよく耳を傾けてくれます。現在は、仕事を続けて3年以上。「兄は気持ちも安定しているようで、家族との会話も穏やかになりました」とショウタさんは安堵の表情を浮かべます。
卒業後の進路は波風の大きい「大海原」
アキラさんが特別支援学校高等部を卒業してからの家族の日々を、「まるで社会という大海原に放り出されたかのようだった」とショウタさんは振り返ります。卒業後に入所した職業訓練校も近場では見つからず、家族が必死で探したうえ、遠方にようやく見つかりました。
その後も支援機関やジョブコーチと連携しながら進路を模索したものの、支援者との相性の不一致や職場トラブル、離職が相次ぎました。「支援困難」と告げられ、家族が絶望したこともあったといいます。
「インターネットや口コミで、ある程度の情報を探すことはできます。でも、支援施設の雰囲気や支援者との相性は、直接行って話してみなければ分からないことも多いのです。母は兄を連れて、多くの支援機関に足を運んでいました。相性の合う支援者との出会いは、地道に探すしかない、というのが家族で見てきた現実です」(ショウタさん)
「特性にもっと早く気づいていたら…」
ショウタさんはこの20年間をこう振り返ります。
「兄にはこれまで、人間関係のトラブルや脱走、スマホトラブルなどいろいろなことがありました。でも、その度に『たまたま起きたこと』『アキラにはもっといろいろできるはず』と私たち家族が期待して思い込んでいたことが、仕事選びの失敗に繋がったと感じています」
その後、ショウタさんと家族は、アキラさんの一つひとつのトラブルは偶然ではなく、特性によるものだと気づき、小さな問題行動が出たときこそ、どんな支援が必要なのか向き合うチャンスと捉えよう、と視点が変わりました。このように向き合うことの積み重ねが、アキラさんが社会と安心して関わるための土台になるとわかったからです。
「兄はようやく自分らしく生きられる場所を見つけられました。そんな様子を見て、家族もほっとしています」(ショウタさん)
本人の特性や周囲の環境、家族のサポートなどさまざまな視点が求められる、障がいのある人の就労選択。もっとも身近にいる家族だからこそ、本人が「得意」や「好き」だと思っていることに目を向けすぎてしまい、それがかえって本人を苦しめる結果になってしまうこともあります。こうしたリアルな声を知ることが、適切な支援の一助になるのかもしれません。
障がい者の「働く場所」をサポート 10月スタートの新サービス
ご紹介してきたように、これまでは障がいのある人が働こうとする際、職場とのマッチングや定着に際して様々な課題がありました。こうした課題を解消するため、2022年10月に改正された障害者総合支援法に基づき、2025年10月から新しい障害福祉サービス「就労選択支援」が導入されます。
本人の希望や特性、家族や地域の状況などを考慮し、現行の就労支援を利用する前段階として、「お試しで働いてみる」機会を設け、支援機関とともに働きかたを選んでいく仕組みです。特性に合った働き方を見つけるサポートとして期待されています。
障がいのある人の働き方には、現在、企業の障害者雇用枠などで働く「一般就労」や、主に「就労継続支援A型」と「就労継続支援B型」に分かれる「福祉的就労」があります。
一般就労とA型は勤務先と雇用契約を結び、最低賃金以上の給与が支払われます。A型・B型は福祉サービスの中で運営されており、配慮のある職場環境で働くことができます。
A型とB型の最大のちがいは雇用形態です。B型は雇用契約を結ばず、工賃と呼ばれる報酬が支払われる働き方です。時間や仕事内容の自由度が高い一方で、工賃の全国平均は月額2万3053円に留まります(2023年度、厚生労働省)。A型の全国平均月額8万6752円と比べると収入は限られるなか、B型を選ぶ人が最も多いのが現状です。