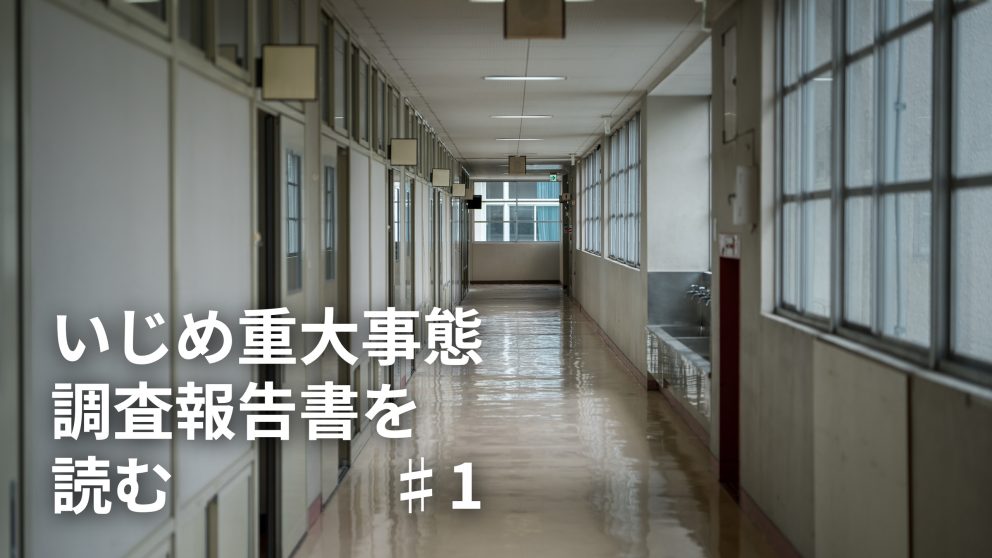「合理的配慮」を考えるとき、土台となるのが「障害とは何か」という定義の変化です。障害を個人の問題とする医学モデルから、社会との関係性に目を向ける社会モデルへ、さらに両者を統合したモデルへと進んできました。
変遷をたどりながら、教育現場における合理的配慮の意義を明らかにします。解説は子どもの発達科学研究所 主任研究員の大須賀優子です。
環境とのミスマッチに注目する「社会モデル」
近年、障害のとらえ方は大きく変化しています。
かつて障害は「個人の心身機能に生じた問題」とされ、医学的治療やリハビリを通じて改善すべき対象と見なされてきました。これが「医学モデル」です。
医学モデルの視点は、本人の努力や専門家の介入に重きを置くため、社会の側が持つバリアにはほとんど注目が向けられませんでした。
しかし1990年代以降、欧米を中心に新たな考え方が登場しました。それが「社会モデル」です。
社会モデルは障害を、個人の身体や認知の特性そのものではなく、「身体的な多数派にカスタマイズされた社会環境(建物・道具・制度・慣習・言語・価値観など)と、少数派の身体を持っている個人との間に生じるミスマッチ(熊谷晋一郎,2021)」と考えます。
たとえば、足が不自由な子どもが階段しかない学校で移動できないとすれば、それは「身体の問題」というより、「環境の不備」による問題だと考えるのです。
この考え方は、建築や交通の整備、ICTの開発などにも大きな影響を与え、社会環境の改善を後押ししました。
障害を「社会の課題」と位置づけることで、当事者の権利を守るための政策や取り組みが広がっていったのです。
「統合モデル」という新しい考え方
ただし、社会モデルだけでは説明しきれない部分もあります。
たとえば、リハビリや医療的ケアによって本人の機能が改善すれば、生活の質は大きく向上します。社会的バリアの除去に目を向けるだけではなく、身体的な機能が改善できるのであればそのアプローチも無視するべきではありません。
こうした背景から、WHOが2001年にICF(国際生活機能分類)で採択しているように、現在では「統合モデル(総合モデル)」と呼ばれる見方が主流になっています。
統合モデルは、障害を「個人の特性」と「社会環境」の両面からとらえ、その相互作用に注目します。つまり、障害を軽減するための支援として、個人の機能に働きかける医学的支援と、社会的バリアを取り除く環境整備の両方が重要だという考え方です。
統合モデルの視点は、教育現場での特別支援教育の基盤ともなります。子どもたち一人ひとりの発達や特性に応じた教育を行うと同時に、学校という環境そのものを柔軟に整えることで、学びの機会を保障するのです。
障害を個人ではなく社会全体の課題ととらえ、暮らしやすい環境を整える
具体例で考えてみましょう。発達性協調運動症(DCD)という特性がある幼児を例にとります。
DCDは、知的な遅れがないにもかかわらず、動作のぎこちなさや不器用さによって、日常生活や学習活動に支障が出る神経発達症のひとつです。子どもを支援する際の考え方を「医学モデル」と「社会モデル」の両方のアプローチから見ていきましょう。
- 医学モデルとしてのアプローチ
とある幼児が、幼稚園での一斉の制作活動に参加できない時、背景にある個人の運動機能の課題に対して、丁寧にクレヨンの持ち方やハサミの使い方を教えてできるようにしていくことは、特性に応じた教育として必要なことです。
- 社会モデルとしてのアプローチ
一方で、多様な素材、さまざまな道具、手順の簡略化、時間の余裕、一緒に手を添えて作るといった身体的な支援等の、本人の能力の向上に依らない方法で、「できた!」「みんなと一緒に楽しめた!」という経験を提供していくことも重要です。
社会モデルの重要性は、環境そのものを柔軟に整えることによって、学びの機会や参加の機会を保障し、子どもの意欲を育むことに直結する点にあります。
これは、子どもの発達支援にとどまらず、多様なあり方を受容する社会をつくることにもつながります。
障害を「個人の責任」に委ねるのではなく、社会全体で課題を共有し、誰もが安心して参加できる環境を整えていく。つまり、社会環境を整え、バリアを減らすことで、誰もが安心して関われるようになる。そのこと自体に大きな意味があるのです。
障害を個人だけの問題にしないために
合理的配慮は、このような障害観の視点の変遷を背景に形作られた概念であり、環境そのものを柔軟に、個人のニーズに即して変更・調整していくことに他なりません。
障害を個人の責任や限界として扱うのではなく、また、個人の能力の向上を図るアプローチだけに終始するのではなく、同時に、社会の側を適切に変更、調整することで初めて、「平等な参加」が可能となるのです。
医学モデルから社会モデル、そして統合モデルへ。教育現場では、まさにこうした考え方の転換を理解したうえで日々の実践を行っていくことが求められています。
執筆者:大須賀 優子(おおすか ゆうこ)

- 公益社団法人 子どもの発達科学研究所 副所長・主任研究員
- 博士(小児発達学)
- 所属学会:日本児童青年精神医学会、日本教育心理学会